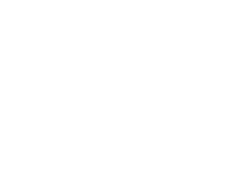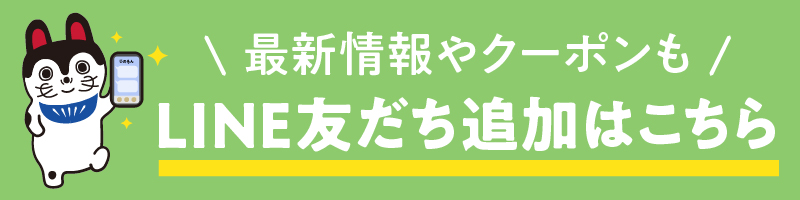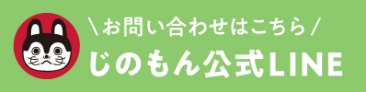日常に、漆器をひとつ。山中漆器の自由な風土が育んだ、等身大の“マイ漆器”
石川県には、加賀友禅や九谷焼をはじめ、たくさんの伝統工芸があります。その中のひとつ、「山中漆器」は、加賀市の山中温泉地区で脈々と受け継がれてきた漆器です。
…と聞くと、ちょっと堅苦しそう? そんなイメージをいい意味で裏切られる出会いがありました。

■“漆器と言えば和食”という先入観を覆す斬新なデザインも多く並ぶ店内。
「漆器って、“お正月にだけ出してくる食器”という印象の人が多いと思います」
そう話すのは、今回お話を伺った『浅田漆器工芸』の浅田明彦さん。
たしかに、漆器といえば思い浮かぶのは赤や黒の重厚感ある和のデザインで、ここぞというときにだけ使うもの…そんなイメージ。どこか敷居の高さを感じていました。
でも、『浅田漆器工芸』さんの商品ラインナップを見ると、どうでしょう。
なんだか、普段使いできちゃいそうな雰囲気ではありませんか。

■最新作はアイスクリーム用の器。真鍮の土台は富山県高岡市の伝統工芸「高岡銅器」によるもの。
新しいものを積極的に。それが山中漆器の“伝統”
こんなカラフルな器まであるだなんて。漆器って、思った以上に自由なんですね…!
そう言うと、「この自由度の高さは、ほかの漆器の産地にはない特長かもしれませんね」
と浅田さん。
ここでは安土桃山時代に木地(漆を塗る前の木で作った器)づくりが始まり、湯治客に売る土産物として発展。外部から塗りや蒔絵の技術を取り入れながら、「山中漆器」のブランドを築き上げてきた歴史があるのだそうです。
「そういう経緯で発展してきたからか、山中漆器にはいいと思ったもの、流行しているものをどんどん取り入れる文化があるんですよ」
かく言う浅田さんも、あたらしい漆器には積極的。
「ある日、わたしの好きな食べ物だからという単純な理由で『カレーやパスタを盛り付けるための漆器が作れないかな?』と思い立ち、試行錯誤を始めたんです」
そして完成したのは、これまでになかった“現代の食卓に似合う漆器”でした。
洋食にも使えるデザインはたちまち人気を集め、現在ではメタリック塗装を施したシリーズなども展開。新たなファン層の獲得に繋がっていると言います。

■ろくろを回しながら木を削っていく「挽物木地」の技術は、山中漆器の特長のひとつ。
技術の積み重ねでこれからの時代も
革新的なデザインは、歴史に裏付けされた技術があってこそ。
いまの暮らしの中での使いよさを重視しつつ、山中漆器の伝統技法を感じられる器も数々取り揃えています。
たとえば、「拭き漆」という漆の塗り方。漆を塗ってはふき取る工程を繰り返すことで、うっすら木目が透けた仕上がりに。山中漆器の特長である木地の美しさが堪能できる器になるといいます。

■たまゆらカップ
卵のようなころんとした形が愛らしいこちらの「たまゆらカップ」、外側はメタリックカラーですが、内側は拭き漆。お茶にもコーヒーにも合いそうな今っぽいデザインと、山中の伝統技法の両方が楽しめる器です。

■SUWARI叢雲塗
山中漆器の技術の粋を集めたフラッグシップモデルと言える器も。
このカップに用いられているのは「叢雲塗」という漆が固まる前にろうそくの煤を付けていく手法。これができる職人は、いまの山中ではたった一人だけなのだそう。
炎のゆらぎがそのまま黒い模様として映し出された、偶然の美。
「今日はちょっぴりいいお酒を」。そんな日に、特別な時間を演出してくれそう。
日常に漆器を。
「漆器も、ふつうに使っていいんだよと伝えたい」
と、浅田さんは言います。
「食洗器や電子レンジは避けたほうが長持ちしますが、それ以外は特別に気を遣う必要はありません。洗剤で洗って自然乾燥で大丈夫です」
使ううちに色が褪せてきたら塗り直しができ、飽きたら違う色に塗り替えだって可能。ひとつの器を、長いあいだ使い続ける楽しみがあります。
「伝統工芸品」と身構えず、日常の中で”ふつう”に付き合っていけばいいんだなと安心したら、我が家の食卓にも並べてみたくなりました。
みなさんもマイ漆器、お迎えしてみませんか?

■「常識にとらわれず、時代に合った表現を探求することで、伝統は続いていくものだと信じています」と浅田さん。これからの山中漆器も楽しみです。
<じのもんオンラインショップで販売中>
浅田漆器工芸
0761-78-4200
石川県加賀市山中温泉菅谷町ハ215
営/9:00~17:00
休/なし
[Instagram]@ asada_shikki1976 ※外部サイトに遷移します
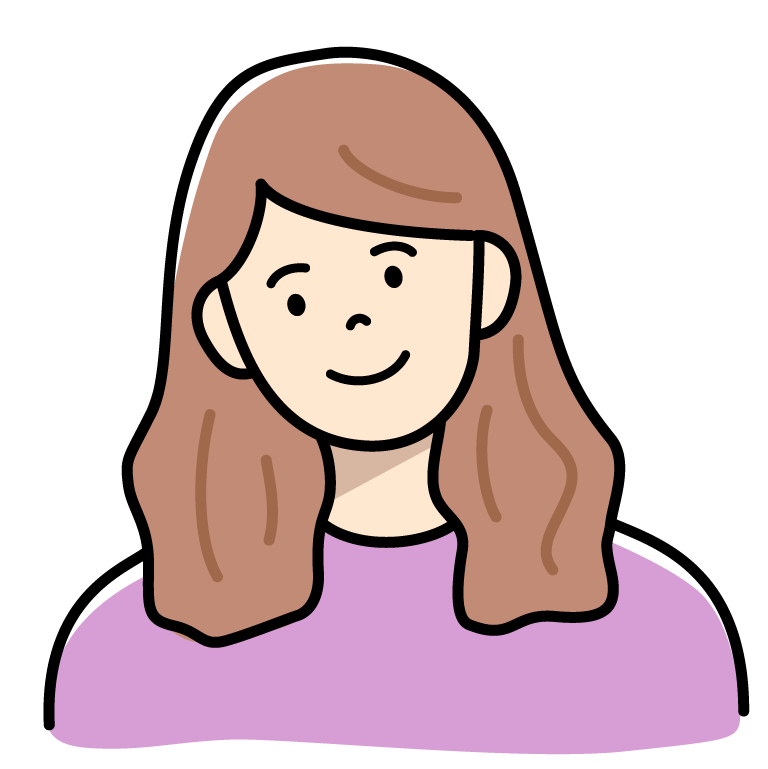
じのもんライター:中嶋 美夏子
大学進学を機に金沢へ。おいしい食べ物と暮らしに根付く美意識に感動し、日々探求しているうちにいつの間にか十数年が経ってしまった。人々のなにげない日常が撮りたくて、ちょっとしたお出かけでもいつもカメラと一緒。能登からやってきた保護猫とふたり暮らし。