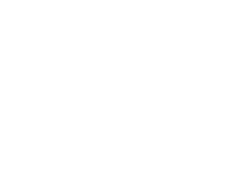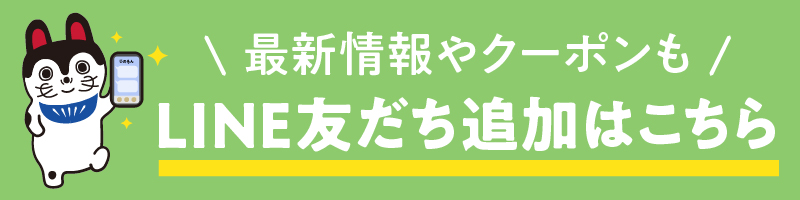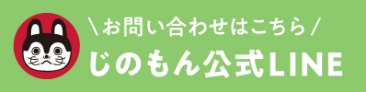『能登製塩』が作るミネラルたっぷりの塩と「塩屋のスープ」。珠洲の海からの恵みをふたたび人々のもとに。
料理がうまい人は、塩にこだわりを持っている…そんな印象ありませんか?
そのイメージ通り、食通や料理人から根強い人気があるという『能登製塩』の塩。
珠洲の海水をくみ上げて特別な製法でつくられるといいますが、震災の影響で工場の稼働が困難に。再建に向けて一歩ずつ歩む現在についてお聞きしました。

■能登半島の沿岸には「塩街道」と呼ばれる国道249号線が。(※画像は能登半島地震以前のものです)
石川県の先端、珠洲市。
ここに工場を構える『能登製塩』さんは、独自の製法によってこだわりの塩「奥能登海水塩」を作っています。
珠洲の海から海水をくみ上げて、50℃以下の温度でゆっくりと海水を温め、4昼夜かけて塩の結晶をつくり出す「非直火低温製法」。一般的な高温加熱の製塩方法では取り除きにくい不純物を丁寧に除くことができるのが、この製法の特長です。
90種類以上のミネラルを含むことから強いうま味が感じられ、しかも雑味がない。この塩でなければ!という根強いファンが多いというのも頷ける、深い味わいです。

■海岸隆起によってできた陸地。遠くに見えるのが製塩工場で、以前は建物のすぐそばまで波が打ち寄せていたのだといいます。
能登半島地震で変わってしまった珠洲の海の姿
『能登製塩』をはじめとする製塩業者が立ち並ぶことから「塩街道」の名で親しまれているという、海岸沿いの国道249号線。能登半島地震では大きな被害に見舞われました。
地震のあった数日後には無事に工場長と連絡が取れ、工場の無事も確認。
ただ、そのとき工場長が口にした「海岸が遠くなった気がする」という言葉が、のちに現実であることがわかります。
地震によって海岸が隆起し、これまで海だった場所が陸地に。海が、100メートル以上も遠くなってしまったのです。
「もとは海底だった場所ですから、大きな岩石がごろごろとあり、まともに歩けません。天気が悪い日は波風がおそろしく感じる」
取材のなかで、現場の状況をそう話してくれました。
大きな課題となったのが、塩づくりに欠かせない海水の取水です。
ずっと遠くに離れてしまった海から海水をくみ上げるには新たな設備が必要。対応に追われる日々でした。
「なんとか塩が作れるようになりましたが、取水方法が従来とは変わってしまったことで、製塩量は半分ほどに。道路も十分に整っておらず、塩の運搬にも支障がある状況です」
近隣の商店も営業できないままで、働く環境にも課題が残るままだと言います。

■国産野菜をたっぷり使ったスープの素がもなかに入っています。(※写真は商品の仕様が一部異なります)
能登の塩がアクセントになった、優しい味わいのもなかスープ
工場の再開に奔走するさなか、当時の社長、加藤典子さんが逝去。さまざまな困難が重なりました。
そんな加藤さんが生前に企画した商品のひとつ「もなかスープ」は、自社の塩を使った商品のひとつとして、現在も大切に受け継がれています。
ころんと可愛らしいもなか。中にはスープの具が詰まっていて、お湯をかけるだけでやさしい味わいのスープができあがり。米粉で作られたもなかも、香ばしいクルトンとしてスープの美味しさを引き立ててくれます。
自慢の塩をベースに、化学調味料を一切使わない自然の味わい。使用する野菜は国産の原料にこだわり、素材そのものの美味しさが感じられる仕上がりです。
自然がもたらしてくれる美味しさを丁寧に引き出すというのが、このもなかスープにもお塩にも共通する『能登製塩』さんの哲学のように感じられました。
「塩街道」の歴史を絶やさぬよう、地域全体でも少しずつ再建が進んでいるという現在。
珠洲の海、そして塩を作る人々と会いに、いつかこの地を訪れてみたいものです。

■自慢の塩が野菜の持つ美味しさを引き出します。
<じのもんオンラインショップで販売中>
有限会社能登製塩
076-280-3322
石川県金沢市寺町1丁目6-54
営/9:00~17:00
休/土曜、日曜
[Instagram]@ notoseien ※外部サイトに遷移します
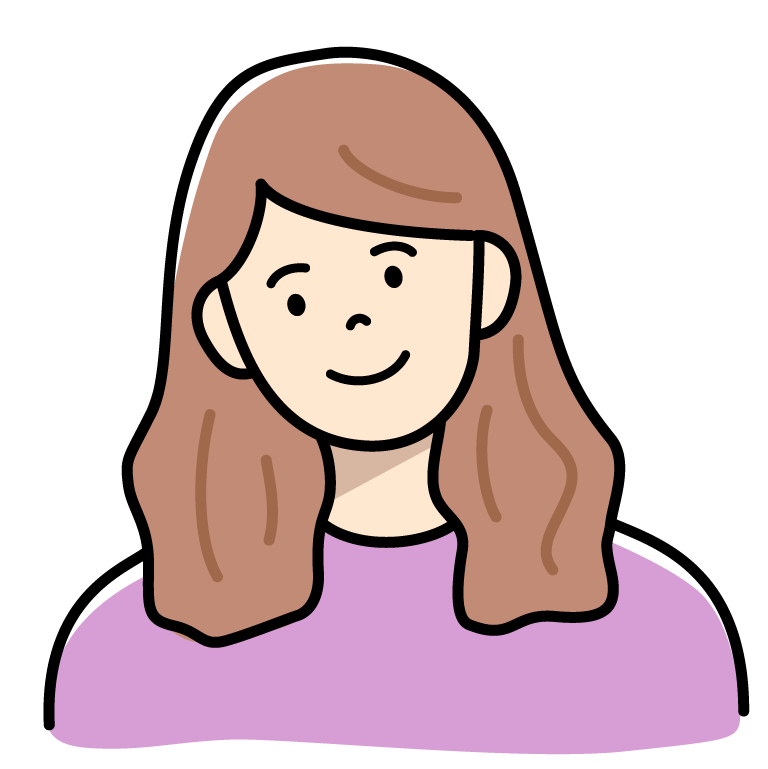
じのもんライター:中嶋 美夏子
大学進学を機に金沢へ。おいしい食べ物と暮らしに根付く美意識に感動し、日々探求しているうちにいつの間にか十数年が経ってしまった。人々のなにげない日常が撮りたくて、ちょっとしたお出かけでもいつもカメラと一緒。能登からやってきた保護猫とふたり暮らし。